リハビリテーション科医師は、病気やけが、高齢による機能低下などで日常生活に支障をきたしている患者様に対し、機能回復や生活の質(QOL)の向上を目的とした治療を行う専門医です。脳卒中や脊髄損傷、骨折、関節疾患、神経難病など、幅広い疾患に対応し、患者一人ひとりの状態に合わせたリハビリ計画を立案・指導します。リハビリテーション科医師の役割は、単に身体機能の回復を目指すだけでなく、患者が社会復帰や自立した生活を送ることを支援することにあります。そのため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリスタッフ、看護師、介護職、ソーシャルワーカーなど多職種と連携し、包括的なリハビリテーション医療を提供します。また、住宅改修のアドバイスや福祉用具の選定など、生活環境の整備にも関与します。医師の診察では、患者の身体機能や日常生活動作(ADL)の評価を行い、回復の見込みや最適なリハビリ方法を判断します。さらに、患者や家族への説明を丁寧に行い、リハビリの目標を共有することも重要な役割の一つです。リハビリテーション科医師は、単なる治療だけでなく、患者の人生に寄り添い、その人らしい生活を取り戻すためのサポートを行う医療の専門家です。リハビリテーション部では、最新の医療技術と温かいチーム医療で、一人ひとりの「みらい」を支えます。
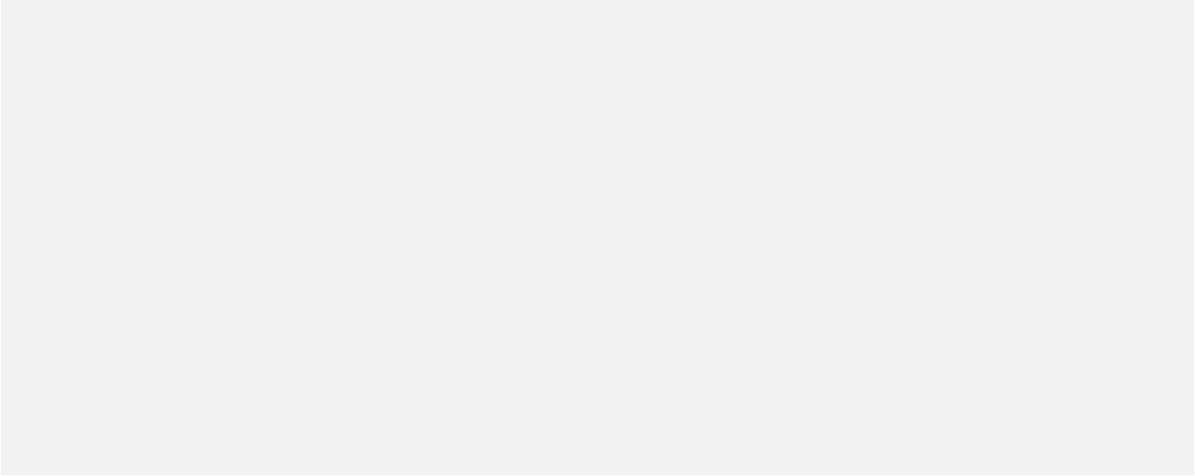
リハビリテーション科の看護師は、患者様の日常に最も近く寄り添う存在です。特に夜間のご様子を把握しているのは看護師であり、病棟での生活を通して、お一人おひとりの回復を支えています。通常の看護業務(採血・検温など)に加えて、退院後の生活を見据えたサポートを行うのがリハビリテーション科の看護師です。お食事や洗顔・歯磨き、更衣、入浴などの日常動作を丁寧に観察し、リハビリで習得した動作が実生活でどのように活かされているかを確認。「病院の中だけできる動作」ではなく、「ご自宅でもできる動作」へとつなげていくことを大切にしています。そのために、多職種と連携しながら、より良いサポートの方法を考えていきます。また、患者様の心理的な変化にも目を配り、リハビリへの意欲を引き出すことも大切な役割です。気持ちが前向きになることで、回復のスピードが変わることもあります。当院では、患者様の活動度を維持・向上させるために、医師の許可が下りた方には、リハビリの時間以外でも看護師が付き添いながら歩行をサポートしています。ただ歩くだけではなく、お一人おひとりの状態に合わせた適切な介助を行うため、療法士とも連携しながら進めています。リハビリテーション科の看護師は、単に医師の指示を実行するだけではなく、患者様の「その先の生活」を見据え、ご家族の皆さまとともに支えていく存在です。退院後の生活について、不安やご質問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
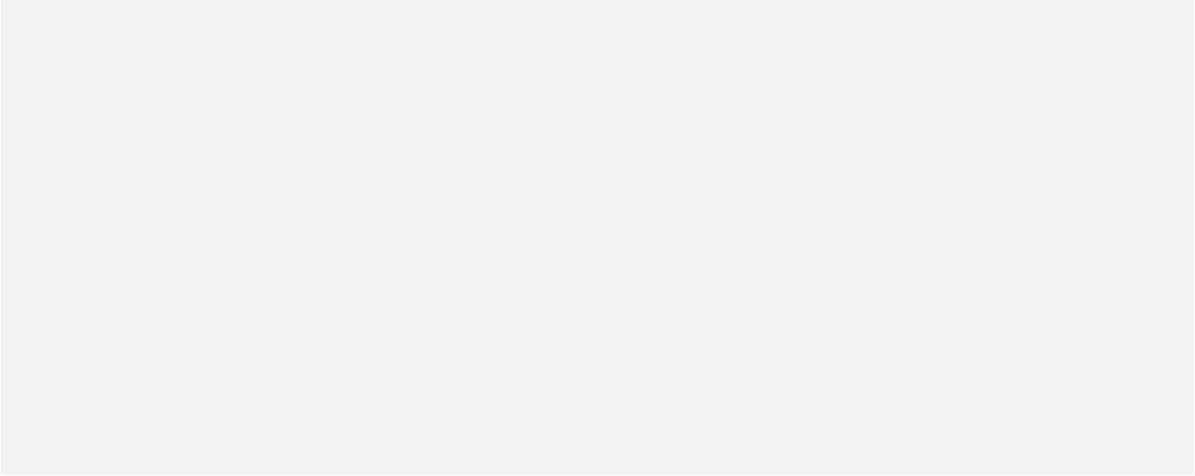
理学療法士(PT)は身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。当院では、患者様がより安全に早期にリハビリができるように歩行支援型リハビリテーションロボット(ウェルウォーク-WW2000)を導入し歩行練習を行い適切な活動範囲を広げる提案を行います。移動の自立は、退院後の生活の質に大きく影響する重要なポイントです。正確な評価と細やかなサポートを行い、患者様が少しでも安心して日常生活に戻れるよう尽力してまいります。

作業療法における「作業」とは、家事・仕事・余暇活動など、人が日常生活で行うすべての活動を指します。当院では、患者様が生活の中で必要な動作をスムーズに行えるよう、身体機能面だけでなく、精神機能面の改善、日常生活に欠かせない行為や社会参加に向けた訓練を実施しています。
食事・着替え・入浴・排泄などはリハビリ室に限らず、病棟など実際の生活場面で訓練を行い日常生活動作の習得を図ります。理学療法士や社会福祉士と連携し、ご自宅を訪問(家屋調査)し、手すり設置や段差解消、福祉用具選定など介護サービスの活用を提案します。
調理・掃除・外出などの生活動作や職場復帰に向けた評価・訓練を実施しています。当院では自動車運転支援を行っています。運転に関わる理解力や注意力などの高次脳機能訓練やドライビングシミュレーターを使用した運転支援を実施しています。また、その方の生きがいや趣味などが継続して行えるよう必要な訓練を行います。
作業療法士(OT)は看護師、介護スタッフと連携し、移乗・歩行・入浴動作を評価し、自立支援を行っています。適切な介助方法を多職種で共有、協働し患者様の能力向上を図っています。

言語聴覚士(ST)は、ことばや発声・発音の障害、飲み込みの問題(摂食・嚥下障害)、高次脳機能(記憶や注意力)の低下に対する評価とリハビリを行います。脳卒中や頭部外傷の影響は外見では分かりにくいこともあり、検査を通じて状態を把握し、それぞれに適した訓練を実施します。また、ご家族と一緒にリハビリを進め、症状の理解を深めながら、日常生活でのサポート方法や復職に向けた支援も行っています。さらに、STは看護師や介護スタッフと連携し、食事の際の安全な摂取方法を検討するほか、他のリハビリ職と情報を共有し、最適な支援ができるよう調整します。患者様が安心して生活を送れるよう、全力でサポートいたしますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。